昨日は、思いがけない涼しさに肩をすくめるような朝だった。
なかなかベッドから起き上がれず、ふと台湾・松山で撮った割包屋さんの店先の写真を見返し、湯気が立ちのぼる屋台の風景と、あの白くふわふわした蒸しパンの感触。
まるで、遠い日の空気が一瞬だけ戻ってきたような気がした。
台湾旅行に行ったのは2017年。もう七年以上も前のことだ。
友人二人との旅で、それぞれが“どうしても行きたい場所”を持っていた。
だから、グループ旅行といっても、途中で自由時間を設けて別行動をすることにしていた。
私は観光地よりも「その土地の人が日常的に食べているもの」を見つけるのが好きで、昼食を求めて一人、松山の街へ向かった。
当時の記憶をたどると、松山空港の近くにいたはずだ。
利用する予定もなかったのに、なぜか空港の売店でお土産を選び、
さらにフードコートでフォーを食べた。
お腹はそれほど空いていなかったのに、旅の高揚感が食欲を呼び起こしたのだと思う。
旅先では、胃袋までがいつもより大胆になる。
「せっかく来たのだから」と自分に言い訳をして、箸を進める。
きっとあの時の私もそうだった。
街をぶらぶら歩いていると、蒸籠の匂いに引き寄せられるようにして、その割包屋を見つけた。
記憶の中の店先は、派手な装飾もなく、どこか素朴で、
看板の下に小さな屋台風のカウンターがあった。
「ここで食べていこう」と思ったのは、ほんの気まぐれだったけれど、
その気まぐれが忘れられない味を連れてきてくれた。
注文を済ませてから店内に入ると、
人の流れは落ち着いていて、テイクアウトを待つ人がちらほら。
異国の地で、ひとり初めてのお店に座る。
その瞬間のわずかな緊張と高揚を、今も鮮明に覚えている。
聞き慣れない言葉が飛び交う空間で、
自分だけが時間の隙間にぽつんと置かれたような不思議な感覚。
けれど、それがとても心地よかった。
目の前に運ばれてきた割包は、
長崎の「角煮まんじゅう」に似た見た目だった。
しかし、一口かじるとまったく別の世界が広がった。
柔らかな豚の角煮に、高菜の漬物、香ばしいピーナッツ粉、
そして何よりも、ふわりと香るパクチー。
甘さとしょっぱさ、そして香草の独特な風味が混ざり合い、
口の中が小さな異国になった。
食べ進めるたびに、頬の奥がじんわりと温まっていく。
白くてやわらかい蒸しパンは、まるで湯気のかたまりのようだった。
両手でそっと包むと、指の先までそのぬくもりが伝わってくる。
旅先でそんな一品に出会えることほど、うれしいことはない。
この割包を見ると、いつも思い出す映画がある。
「在りし日の歌」という中国映画だ。
その中に、家族が朝食を囲むシーンがある。
湯気の立つテーブルに、割包がいくつも並んでいる。
それを各々が手に取り、無言で頬張る。
日本でいうところの“白飯”のような存在なのだろう。
家族の何気ないやり取りと、ふわふわの蒸しパンの白さ。
画面越しに伝わる温度が、なぜか胸の奥をくすぐる。
私はその場面がとても好きで、
ふと割包を見るたびにそのシーンを思い出してしまう。
食べ物には、記憶を呼び覚ます不思議な力がある。
台湾の街角で食べたあの一口が、
今こうして、涼しくなった日本の夜にまで私を連れ戻す。
あのときの湯気、あの匂い、
そして異国の風のざらついた肌触りまで思い出せる気がする。
写真を投稿しただけで、そこまで鮮やかに蘇るのだから、
人の記憶というのは本当に不思議なものだ。
旅をするたび、私は“味の記憶”を集めているのかもしれない。
ガイドブックに載らないような小さな店や、
通りがかりの屋台の一皿。
それらは帰国して時間が経っても、心のどこかで静かに湯気を立て続けている。
味はもう正確には思い出せないけれど、
その時の自分の高揚や孤独、
目の前に広がる街の匂いだけは、確かに残っている。
いつかまた台湾に行けたら、
あの松山の割包屋を探してみたい。
もう同じ場所にあるかどうかも分からないけれど、
その道を歩くだけで、きっと何かを取り戻せる気がする。
旅の記憶というのは、案外そんなふうに
何気ない食べ物の中に生き続けている。
そして、ふとした涼しい夜に湯気を恋しく思うとき、
その記憶たちは、静かにこちらへ戻ってくるのだ。



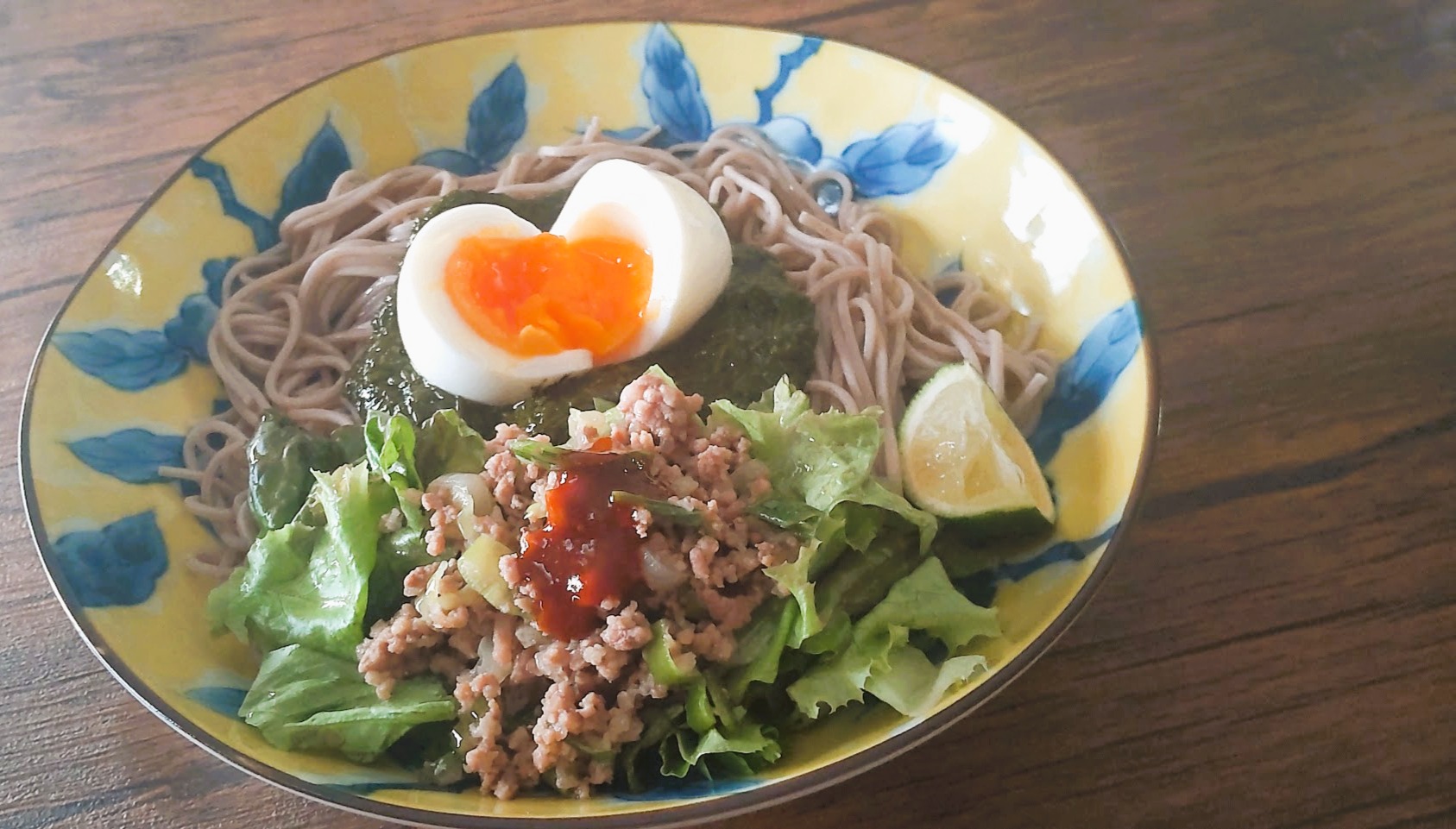
コメント